
更新情報
2025年06月15日 社長ブログ 社長コラム
情意投合の家づくり:想いが通じ合う10の対話 ~誰主導で家づくりをするのか?~
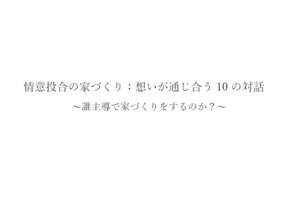
●情意投合とは
「情意投合」とは、
「お互いの気持ちが通じ合い、理解し合えること」
家づくりという人生の大きな決断において、
住宅会社と施主がこの“情意投合”を果たせるかどうかは、
完成した家の満足度を大きく左右します。
本シリーズの1回目では、
「誰が主導して家をつくるのか?」
という視点から、
この情意投合の本質について掘り下げてみます。
■ 家づくりの「主導権」は誰が持つべきか?
注文住宅を検討する際、
依頼先にはさまざまな選択肢があります。
・工務店
・建設会社(大規模建築が主、戸建ては稀)
・設計士
・不動産業者(仲介がメイン)
・分譲業者(規格住宅が中心)
こだわりのある注文住宅を望む方にとっては、
現実的には工務店か設計士の
二択になるケースがほとんどでしょう。
そしてこの選択の先には、
以下のような3つのパターンがあります。
A:工務店主導で進むパターン
B:設計士主導で進むパターン
C:お客様が自分で全て決めていくパターン
■ 設計士主導は「餅は餅屋」で納得できることも多い
設計士主導(Bパターン)の場合、
比較的ズレは少なくなります。
なぜなら、「考えること」が設計士の本業だからです。
ただし、設計士にもさまざまなタイプがいます。
・性能や構造に疎く、デザインだけを重視する人
・技術と感性を両立して、思わず唸る設計をする人
後者のような方と出会えれば、それは幸運です。
■ 工務店主導は「見た目」だけで選ばない
では工務店主導(Aパターン)はどうか?
ここには少し注意が必要です。
現在の住宅会社選びでは、
Instagramなどのビジュアル訴求が
中心になりつつあります。
「この会社、おしゃれ!」
「写真が素敵!」といった
第一印象で選ぶ方も多いでしょう。
でも、SNSで映える写真は、あくまで“見せ方”。
設計意図や技術力まで伝わるものではありません。
実際にはこういう声もよく聞きます:
「なんかイメージと違う」
「話してるうちに違和感が出てきた」
「プランがワンパターンで融通が利かない」
この違和感の正体は、
主導権が誰にあるかの
不一致にあるのかもしれません。
■ お客様主導のCパターンにも落とし穴がある
「自分の家なんだから全部自分で決める」
という考えも一理あります。
でも、情報が溢れる時代では、
取捨選択の責任が施主に集中しやすいのです。
本来プロが導くべき領域まで、
「お客様が決めてください」
と丸投げされてしまうこともあります。
■ 情意投合には「主導のバランス」が欠かせない
施主の希望をすべて聞き入れるだけの会社では、
「プロとしての提案力」が感じられず、
結果的に物足りなさが残るかもしれません。
かといって、工務店が一方的に主導権を握って
「いや、それよりもこの仕様の方がいいですよ」
と進めてしまうのも違う。
理想は、
プロの導きと施主の想いが交わるところにある。
それこそが「情意投合」であり、
家づくりが「自分ごと」として育っていく
出発点だと私は思います。
■ 最後に──
主導権を渡す前に、ひとつ考えてほしいこと
その家に住むのは、住宅会社でも設計士でもありません。
毎日を過ごし、ローンを支払い続けるのは、あなた自身です。
もし、誰かに全部決めてもらう家でいいなら、
センスのいい建売住宅でも充分かもしれません。
でも、それでは「あなたらしさ」は宿らない。
注文住宅とは、「誰かに任せる」ことではなく、
「一緒につくる」ことを選ぶ家づくりだと、
私は思っています。
●まとめ:
・注文住宅には「誰が主導するか」が重要な鍵
・プロ主導でも施主主導でもバランスを欠けば情意投合は起きない
・主導権は「任せる」のではなく、「共有する」もの
次回の情意投合シリーズでは、
「どこまで口を出すか?どこから任せるか?」
という「干渉と信頼」の境界線について掘り下げていきます。




