
更新情報
2025年06月18日 社長ブログ 社長コラム
不定期シリーズ:AIに聞いてみた「軒の出ていない家はどう思いますか?」
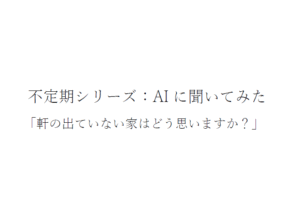
AIの進歩は目まぐるしいスピード感で進んでおります。
今までの日常生活や勉強、
仕事の常識を変えるツールだと思います。
それでもAIを全て受け入れる事が
出来ない方もおられますが、
完全否定は到底出来ません。
AIの情報元は今までの過去膨大な
データベースから最適な回答を出してくれます。
今回のシリーズではAIに家づくりにおいて
様々な質問をしてみたいと思います。
○今回の質問
「軒の出ていない家はどう思いますか?」
●回答
軒(のき)の出ていない家には、メリットもありますが、
明確なデメリットも存在するため、
設計意図や立地条件によって慎重に判断すべきです。
(軒が出ていない家のメリット)
・現代的でシンプルなデザイン
スタイリッシュでモダンな印象を与えるため、
都市部の狭小地などで好まれることがあります。
・建物の形状がコンパクトになる
・敷地ギリギリまで使いやすくなる(狭小地に有利)。
・建築コストが少し下がる場合も。
・施工が比較的簡単
・雨樋や屋根の納まりがシンプルになる場合もある。
(軒が出ていない家のデメリット)
・外壁が傷みやすい
・雨風・紫外線が直接外壁に当たるため、
劣化が早く塗装や張替えの頻度が上がる傾向があります。
・結果的に修繕費が高くつく可能性がある。
・日射遮蔽(しゃへい)が不十分
・夏場に直射日光が入りやすくなり、室温上昇 → 冷房費増加。
・軒や庇(ひさし)があれば、
夏の高い日差しを遮りつつ冬の低い日差しを取り込む
「パッシブ設計」が可能。
・雨水の跳ね返りで基礎や窓が汚れやすい
・外壁だけでなく、基礎やサッシまわりの劣化にもつながる。
■結論
軒の出ていない家はデザイン的な魅力はありますが、
「長持ち・快適・経済的」という観点では注意点が多いです。
特に日本のように雨が多く湿気の高い気候では、
軒のない設計はメンテナンス重視でしっかり補う必要があります。
ご自身がどんな暮らし方を重視しているかによって、
軒の有無の選択も変わってくると思います。
以上になります。
如何でしょうか?
メリットは6個でデメリットは8個でした。
AIやりますね、、笑
私は軒は必ず出した方がいいと思って
日々家づくりをしてきましたし、
今後もしていきます。
ですので、
今回のAIの回答には納得しました。
メリットである内容で気になった点を
AIに人間が質問しました。
・敷地ギリギリまで使いやすくなる(狭小地に有利)。
○質問
「狭小地で有利という事ですが、民法はどうなりますか?」
●回答
非常に良い質問です。軒の出が狭小地で有利なのは事実ですが、
日本の民法(第234条)では、「隣地との距離」に関して
建物の壁またはこれに類するものは、
境界線から50cm以上離さなければならないと定められています。
ここで注意すべきなのが、
軒も「これに類するもの」とみなされることです。
◆民法第234条のポイント(建築基準法とは別)
条文 内容
第1項 建物を築造する場合は、
境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
第2項 地域によって慣習がある場合、それに従う。
第3項 隣地所有者の承諾がある場合は、距離を短くできる。
◆ 軒の出と民法の関係
軒が隣地に向かって出ている場合、
その先端も「境界線から50cm以上」必要になります。
逆に言えば、「軒を出さない」ことで、
建物本体をギリギリまで寄せられるため、
有効面積を最大化しやすいという利点があります。
ただし、これは「隣地側に軒が出ない」場合。
道路側や自分の敷地内方向への軒出しは問題ありません。
◆補足:建築基準法との違い
民法は「隣人関係のルール(私法)」として
最低限の配慮を求めており、
建築確認申請の審査では見られないことが多いです。
しかし、建築後に隣地トラブルになれば、
撤去・損害賠償などを求められる可能性があります。
■ 結論
軒を出さなければ建物を敷地境界ギリギリまで寄せやすくなり、
狭小地では大きなメリットです。
ただし、隣地トラブルを防ぐためにも、
民法上の規定は必ず意識して設計するべきです。
必要に応じて隣地所有者の承諾を得ることも考えましょう。
設計の段階で、
建築士さんに民法配慮の図面になっているか
確認すると安心です。
以上です。
つまり、詳しく質問をすると、
メリットと思われた事でも
デメリットがあったという事になります。
もちろんAIの回答であった、
「狭小地に有利」とはその通りですし、
軒を出さないからこそ、
建築可能の立地条件もあります。
しかし莫大なデータベースからのAIの回答でも
際立ったメリットは無いように感じました。
最後は「どう心が感じたか?」が正解のような気がします。
この情報がお役に立てれば幸いです。




