
更新情報
2025年07月18日 社長ブログ 社長コラム
情意投合の家づくり:想いが通じ合う10の対話 ~使う人のことを考える~
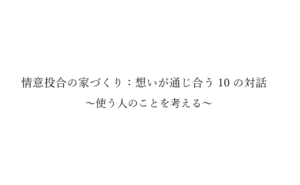
●情意投合とは
「情意投合」とは、
「お互いの気持ちが通じ合い、理解し合えること」
家づくりという人生の大きな決断において、
住宅会社と施主がこの“情意投合”を果たせるかどうかは、
完成した家の満足度を大きく左右します。
前回のコラムでは、「信頼できる住宅会社の見分け方」として、
情報ではなく感情で読み解く重要性をお伝えしました。
では、その「感情の信頼」はどこから生まれるのか?
今回は、私たちが家づくりの現場でずっと大切にしてきた視点、
「使う人のことを考える」ことの価値について、
改めて綴ってみたいと思います。
■ その気づかい、誰のため?
トイレでペーパーの先が三角に折られているのを見ると、
私はいつも少しだけ、あたたかい気持ちになります。
マナー、見た目、美意識。
理由はいろいろあるけれど、
本質は「次に使う人への配慮」だと私は思っています。
その小さな気づかいに触れたとき、
見えないけれど確かにある想いを感じるのです。
■ ディテールの意味は「心」で決まる
家づくりの中にも、
同じような場面がたくさんあります。
・カウンターの角の丸み(R)
・窓台の出幅
・手すりの太さや高さ
それぞれに「なぜこうしているのか」
という理由があります。
見た目だけでは伝わらない、
「使う人の未来」まで想像した設計や施工があるのです。
たとえば角の面取り――
それは「ぶつかったときのケガを防ぎたい」
という想いかもしれない。
手触りの滑らかさは、
「毎日触れる場所に気持ちよさを」
という願いかもしれない。
■ 性能にも、思いやりは宿る
断熱や気密、耐震性能。
数値で語られるこれらの要素も、
ただの“基準”ではありません。
・冬に寒くないように
・夏に体がだるくならないように
・地震が来ても、大切な人を守れるように
そのすべてが、「使う人を思う気持ち」の
延長線にあります。
私たちが性能を追い続けてきたのは、
数値競争のためではなく、
「安心して暮らせる日常」を守りたいからなのです。
■ 素材の選択には、理由がある
例えば「そとん壁」や「サーモウール」。
私たちは創業以来、
200棟以上の家で使い続けています。
理由はただひとつ。
「家族がずっと健やかに暮らせる家をつくりたいから」
・化学物質に敏感な方でも安心できること
・湿度調整や断熱性で快適な住環境を維持できること
・経年劣化よりも風合いが増していくこと
住んだあとの未来まで見据えて選んだ結果が、
この素材たちなのです。
■ 高い?――それは何と比べてですか?
「いいのは分かるけど、ちょっと高いですよね」
そう言われることもあります。
でも私は、「何と比べて高いと感じるのか」
を丁寧に聞き返します。
海外で量産された建材を使った規格住宅や量産された家と、
職人の手仕事や自然素材にこだわった注文住宅。
そもそも比較の「ものさし」が違うのです。
■ スプーンにも宿る「使う人へのまなざし」
木のスプーンとプラスチックのスプーン。
同じ「すくって食べる道具」でも、
使う人の感覚はまったく違います。
・木のスプーン:
やさしく、口当たりが良く、温もりがある
・プラスチックのスプーン:
冷たく、硬く、割れやすい
家も同じです。
どんなに形が似ていても、
「誰のために、どんな想いでつくられたか」で価値は変わるのです。
■ 本当の価値は「比較」ではなく「選択」で決まる
似たような間取り、似たような仕様。
でも、「どんな心でつくられたか」は、
家に空気感として宿ります。
・さりげない気づかいが積もった家
・手間を惜しまず、ていねいに育てられた家
・暮らしのこれからを見守るように設計された家
それは価格では測れな情意のかたまりです。
■ 最後に:使う人の人生を、ずっと想像し続けたい
私たちが家づくりをする上で、
ずっと大切にしている問いがあります。
「この家に住む人が、10年後どう暮らしているか?」
「子どもが成長したとき、どんな気持ちでこの家を思い出すか?」
だから、素材も仕上げも、
ひとつひとつに想いを込めて選びます。
それが、「使う人のことを考える」という仕事の本質。
そして、それこそが情意投合の根っこだと、
私は信じています。
●まとめ
・情意投合とは、「使う人の未来に思いを馳せること」から始まる
・性能や素材も、すべては“人のため”でなければ意味がない
・価格の比較ではなく、“誰のためにどうつくられたか”を大切にしたい
・真の価値は、見えないところに宿る
●次回予告(第6回)
次回は、「選択肢があることで、
人ははじめて『選べる』」というテーマです。
最初から見えているものだけで選んでいないか?
本当に納得できる家づくりは、
“知らなかった選択肢”に気づくことから始まります。
榊をきっかけに得た気づきとともに、
「比べて選ぶことの大切さ」を掘り下げていきます。




