
更新情報
2025年07月26日 社長ブログ 社長コラム
情意投合の家づくり:想いが通じ合う10の対話 ~なぜあのときすれ違ったのか~
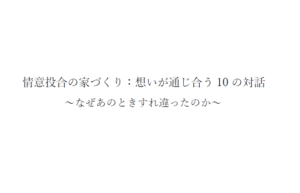
●情意投合とは
「情意投合」とは、
「お互いの気持ちが通じ合い、理解し合えること」
家づくりという人生の大きな決断において、
住宅会社と施主がこの“情意投合”を果たせるかどうかは、
完成した家の満足度を大きく左右します。
家づくりのなかで、
「思っていたのと違った」
「こんなはずじゃなかった」
という声を聞くことがあります。
図面通りに完成した家。
性能にも問題はない。
でも、どこかしっくりこない。
それは、「情意のズレ」が
起きていたサインかもしれません。
■ 「すれ違い」は、ある日突然起こるわけではない
施主とつくり手の関係は、家づくりが進むほど密になります。
しかしその一方で、“小さなズレ”が見過ごされたまま進んでいくと、
完成時に大きな「違和感」として返ってくるのです。
たとえば、
・打合せのたびに出てくる専門用語
・「これで大丈夫です」と言われたから信じた設備仕様
・間取りの違和感を伝えたけど「もう修正できません」と言われた
これらは、「知識の差」や「確認不足」ではなく、
情意がすれ違った結果です。
■ 伝えるべきは理屈より背景にある想い
私たちはよく、
「お客様に説明するときは、
数字だけでなく理由も添える」と伝えています。
たとえば、
「この断熱材は性能が高い」だけでなく、
「お子さんが喘息気味だと伺ったので、
より調湿性に優れた素材をご提案しています」
という言い方です。
数値や理屈ではなく、
「あなたのために選んだ理由」が伝わってはじめて、
お客様との「情意」は重なりはじめます。
■ ズレが起きた現場から学んだこと
以前、あるお客様とのやり取りで、
こんなことがありました。
引き渡しの直前、
「ここの収納、やっぱりもう少し広くしたかったです」
と奥さまに言われました。
私たちはこう思いました。
「何度も確認したし、図面にもサインをもらった」
「直前での変更は物理的に難しい」
でも、そこで気づいたのです。
奥さまは「寸法の問題」を言っていたのではない。
「もっと自分の暮らしに寄り添った提案がほしかった」のだと。
これは、図面や仕様の問題ではなく、
共感の不足によって起きたズレでした。
■ お客様が言葉にできないことを、読み取る力
家づくりでは、お客様自身が「本当に求めているもの」を、
うまく言葉にできないこともあります。
・「なんとなく不安」
・「しっくりこない」
・「どれが正解か分からない」
だからこそ私たちは、
言葉にされなかった感情を、
設計に反映する力が求められるのです。
それが、情意投合という仕事の核心です。
■ 情意のズレは、「丁寧なやりとり」でしか埋まらない
私たちが何より大切にしているのは、
「この人に任せてよかった」と
思ってもらえる関係を築くことです。
そのためには、技術だけでは不十分です。
正確な施工だけでも足りません。
「あなたの想いを、ちゃんと汲み取ろうとしてくれた」
この感覚こそが、
満足や感”の根っこにあると私は思います。
●まとめ
・家づくりの後悔の多くは情意がズレた瞬間に生まれている
・数字や仕様だけでなく、想いと背景を丁寧に伝え合うことが大切
・「言われたこと」より「言われなかったこと」に耳を澄ませたい
・情意投合とは、設計でも工事でもなく、人と人との関係性の仕事である
●次回予告
次回は、情意投合の集大成として
「引き渡しのあとに信頼が本当に試される瞬間」について、
実際のエピソードを交えながら掘り下げます。




