
更新情報
2025年08月17日 社長ブログ 社長コラム
独り言研修シリーズ:忘れについて(前編)
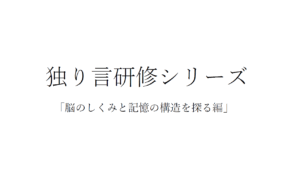
脳のしくみと記憶の構造を探る
「ごめん、忘れてた…」
「何か言われた気がするけど、思い出せない」
そんな経験、あなたにもあるはずです。
今回は、そんな「忘れる」という現象をテーマに、
私自身が社員向けに話した研修内容をベースに、
「脳と記憶の関係性」を探ってみたいと思います。
■ 記憶は3つのステップでできている
人間の記憶は、
以下の3つの段階から成り立っています。
・記銘(きめい):新しい情報を受け入れて覚える
・保持(ほじ):情報を保ち続ける
・想起(そうき):必要なときに思い出す
このうち「記銘」と「保持」は、
ある程度自動的に脳が処理してくれます。
ですが、保持したつもりの情報が
スルスルと抜けていく…
これが、いわゆる
「忘れる」という現象です。
■ エビングハウスの忘却曲線:人はすぐ忘れる生き物
脳の性質を知る上で有名なのが、
「エビングハウスの忘却曲線」です。
これによると、
・20分後:42%忘却
・1時間後:56%忘却
・1日後:66%忘却
・1週間後:75%忘却
・1ヶ月後:79%忘却
という具合に、
人間はものすごい勢いで
情報を忘れていきます。
だから「昨日の昼ごはんが思い出せない」のも、
完全に正常です。笑
■ 記憶はどこに保管されるのか?
人間の記憶は、
脳の中でも2つのエリアを経由しています。
・海馬(かいば):短期的な記憶の保管庫
・大脳皮質(だいのうひしつ):長期記憶の保管庫
まず情報は海馬に一時保存され、
重要と判断されれば大脳皮質に転送され、
数年単位で保持されるようになります。
この転送は睡眠中に起こるとも言われており、
「夢」はそのプロセスの副産物かもしれない…
という説もあります。
■ 脳の記憶容量って、どれくらい?
かつては「脳の容量は17.5テラバイト」
とされていましたが、最近の研究では、
なんと1ペタバイト(1000TB)もの
容量があるとされています。
これは、
・テレビの高画質録画で13年以上分
・米国人口のDNA情報の2倍以上
に相当する容量。
私たち、めちゃくちゃ高性能なストレージを
頭の中に持っているんです。
すごくないですか?
■ じゃあ、なぜ忘れるのか?
海馬から大脳皮質に転送されなかった情報は、
消えていく=忘れるのです。
つまりこういうことになります。
・繰り返し思い浮かべる
・声に出して説明する
・誰かに教える(アウトプット)
こうした行動をとることで、
情報は「これは重要」と判断され、
大脳皮質に保存されやすくなる。
要するに、インプットよりも
“アウトプットがカギ”だということです。
■ でも、全部は覚えられない
どれだけ容量が大きくても、
私たちは毎日膨大な情報にさらされています。
全部を覚えておくなんて、不可能なのです。
だから私は、「覚える」のではなく、
思い出せるようにしておく仕組み作りに
シフトするようになりました。
次回の後編では、
その「思い出すための技術=想起」について、
具体的な方法と日常の
事例を交えてご紹介します。




