
更新情報
2025年08月18日 社長ブログ 社長コラム
独り言研修シリーズ:忘れについて(後編)
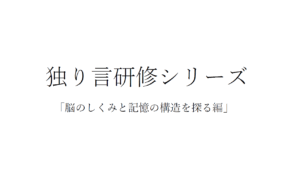
前編では、人間の記憶は
「記銘(覚える)→保持(とどめる)→想起(思い出す)」
この3ステップからできており、
いかに脳が忘れるように
できているかという話をお伝えしました。
では、私たちは忘れてはいけないこと、
忘れたくないことを、
どうやって扱えばいいのでしょうか?
その鍵となるのが、
「想起=思い出すための仕組み」です。
■ 忘却は敵ではない
まず前提として、
忘れること自体は悪いことではありません。
むしろ、忘れることで脳は容量を整理し、
新しい情報を取り込む余白を
作っているとも言われています。
つまり、「忘れる=悪」ではなく、
「必要な時に思い出せない=困る」わけです。
だから私がたどり着いた結論はこうです。
”忘れない努力をするより、
思い出せる仕組みを持っておく”
■ 想起の準備があるかないか
たとえば、日常のあるあるでは、、
例:洗剤、買い忘れ
「洗剤が切れた。帰りにスーパーで買おう」と思う
→ 頭の中に留めたままスーパーへ
→ 献立に気を取られて洗剤を買い忘れる
→ 家に帰って気づく「やってもうた…」
※あるいは洗い物をする際に思い出す
これ、「記銘」はしてるけど
「想起の準備」をしていないから起きるんです。
私たちは、「覚えておこう」と思った瞬間に、
それだけで安心してしまいがちですが、
実はその時点で忘却ルートに乗っています。
■ 想起対策は「技術」である
では、どうすれば思い出せる
仕組みが作れるのか?
私が実践しているのは、
次の5つの「想起トリガー」です。
想起トリガー例
・メモをとる
・スマホのリマインダーに入れる(時刻や場所の指定)
・カレンダーに登録する(繰り返し通知も可)
・他人に伝えておく(言った手前、忘れられなくなる)
・紙に書いて目に見える場所に置く(財布、PC、洗面所など)
ここで重要なのは、記憶しようとする前に、
想起の仕込みを先にやるということ。
これは”今すぐ”しないといけません。
ここでやらなければ、
結局は”忘却曲線”の話になるからです。
覚えておく努力は一切不要です。
「思い出せる仕組み」ができたら、
その時点で忘れていいんです。
■ 私のやり方:「意図的に忘れる」ことを習慣にする
私はリマインダーにタスクを登録した瞬間、
こう決めています。
「よし、もう忘れていい」
そう思うことで、
脳の容量を空けて次に集中できるし、
忘れた頃にリマインダーが
「ピコン」と教えてくれる。
するとその瞬間に、
記憶のスイッチが入る。
「あ、そうやった!」
これが、想起=脳の再起動です。
■ 想起は“再インストール”ではなく“アクセス”である
よく、「思い出す」というと
「もう一度覚える」ようなイメージを持たれますが、
本質的にはそうではなく、
すでにあった情報に
再びアクセスする行為です。
たとえばパソコンでも、
データを削除していないのにフォルダを
探せなかった経験ありますよね?
記憶も同じで、
フォルダの場所さえ指定してあげれば、
出てくるのです。
その場所指定が、
リマインダーであり、
メモであり、
カレンダーなのです。
■ 忘却仕様の脳に「記憶勝負」するのは無謀
脳は20分で42%、
1日で66%を忘れる仕組みです。
この上で「覚えておけば大丈夫」
と考えるのは、無謀です。
■ 忘れる前提で備えておく
「私は記憶力が悪いから…」と
自分を責める人がいますが、
そうではなくて、
単に想起の仕組みを持っていないだけです。
本当に大切なのは、
「どうすれば忘れないか?」ではなく、
「どうすれば思い出せるか?」です。
■ まとめ:記銘→保持→想起を“意識的に仕組化する”
人間の脳は、1ペタバイトもの記憶容量を持っていても、
そこに届ける方法と、取り出す方法が
備わっていなければ意味がありません。
だからこそ、
・記銘:まずは何かを気づく、発想する
・保持:その瞬間、情報を記録するか整理する
・想起:未来の自分が「思い出せる足跡」を残す
この流れを、
意識的に仕組み化する習慣を持つことが、
仕事にも人生にも、必ず役に立ちます。
●最後に
私たちは「忘れる生き物」です。
でもそれを責めるより、
備えることに力を
使った方がずっと健全です。
「記憶」ではなく、
「想起」の質を高める。
これが、忘れ物やミスを防ぐための
最も現実的な方法だと思います。
今日からぜひ、「思い出せる仕組み」を
ひとつだけでも生活に取り入れてみてください。
それだけで、
あなたの忘れは減っていきます。




