
更新情報
NEW
2025年10月27日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「空き家の“使える・使えない”を分ける境界線とは?」
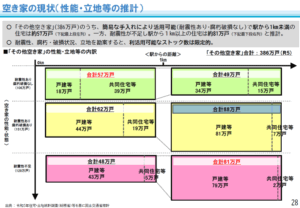
●初めに
日本全国で進行する「空き家の増加」
その存在はニュースなどで
たびたび取り上げられますが、
「数が多い=活用できる」わけではない、
という現実をご存じでしょうか?
国土交通省の資料によれば、
令和5年時点で
「その他空き家」は全国に386万戸。
そのうち
「耐震性があり、腐朽・破損の状況がなく駅から1km未満」
という“最低限使える条件”を満たす住宅は、
わずか57万戸に過ぎません。
全体の約15%です。
この数字は、単に「空き家の数」ではなく、
「活用できる空き家の限界」を示すものです。
●「駅近でも性能不足なら使えない」という現実
空き家問題を語るとき、
よく「リノベーションで蘇らせればいい」
「空き家バンクで移住促進を」
といった意見が聞かれます。
しかし、その前提となるのが
“使える空き家”であることです。
駅からの距離が近い空き家であっても、
耐震性に問題があったり、
構造的に補修が困難だったりすると、
活用するには大規模な改修が必要となり、
コスト・手間・時間の面で
現実的ではありません。
実際、駅から1km未満にある空き家のうち
「耐震性があり、腐朽・破損あり」及び、
「耐震性に問題あり」とされる住宅は
87万戸も存在しており、
57万戸(条件を満たす空き家)を上回っています。
つまり、立地が良くても
「構造性能」が劣っていれば活用は困難。
逆に、耐震性が確保されていても
「駅から遠い」
「アクセスが悪い」住宅は、
活用のハードルが上がります。
これが、「性能×立地」の掛け算でしか
住宅ストックの再活用は成立しない、
という厳しい現実です。
●「戸建て」は特に厳しい。住宅性能の分岐点
特に厳しいのは「戸建て住宅」です。
駅から1km未満の空き家のうち、
「耐震性があり、腐朽・破損もない」
住宅は18万戸。
一方、同じ条件を満たし、
かつ駅から1km以上離れている
住宅は34万戸あります。
つまり、性能は満たしているけれど、
立地面で活用が難しい空き家が
倍近く存在しているのです。
さらに、駅から遠くて、
耐震性にも問題がある
戸建ては79万戸。
この層は「住むには不安」「貸すにも手間がかかる」
「売るにも買い手がつきにくい」という
“負動産”リスクの象徴と言えます。
●「家の性能」は未来の活用可能性を左右する
このデータから導き出せる結論は明確です。
今つくる家の「性能」は、
将来の価値と流動性を決める分岐点である。
家は今住むためだけのものではなく、
将来「売る」「貸す」「相続する」
「リノベして別用途に転用する」といった
可能性を秘めた資産でもあります。
そして、その資産としての可能性を決めるのが、
性能(特に耐震性)と立地です。
これからの時代、
どれだけ魅力的なデザインの家を建てたとしても、
耐震性能が不十分であれば20年後には
「使いにくい」「売れない」「貸せない」
空き家になってしまうかもしれません。
だからこそ、長期的な視点での
“資産価値”を意識した家づくりが、
これからの住宅選びには欠かせません。
●「使えるストック」を未来に残す家づくりを
私たち工務店が担う使命のひとつは、
「使えるストックを増やすこと」だと考えています。
単に今快適な家ではなく、
30年後・50年後に誰かが使いたいと思えるような、
“性能と立地を兼ね備えた住宅”をつくること。
それは「持続可能な住まい方」
「世代を超えて住み継がれる暮らし」を実現するための、
最も実質的で誠実なアプローチではないでしょうか。
未来の空き家予備軍にならないために、
そして、「活かせる住宅ストック」として
資産価値を持ち続けるために、
家を建てる段階から「立地と性能」を両輪で
考える視点が求められています。
●参考出典
国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)
該当ページ:28ページ(空き家の現状(性能・立地等の推計))




