
更新情報
NEW
2025年11月08日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「“超・高齢社会”に応える工務店という選択」
●初めに
いま、日本の人口構造が
大きく転換しようとしています。
2020年時点で65歳以上の高齢者は
約3600万人(全人口の28%)。
この割合は2035年には33%、
2050年には37%を超えると予測されています。
特に「団塊世代」は2035年に
全員が85歳以上、
「団塊ジュニア世代」は2050年には
75歳以上となり、
日本はかつてない
“超・高齢社会”へと突入します。
この現実を、私たち工務店が
“自分ごと”として受け止めているでしょうか?
■「高齢者のための家づくり」ではなく、
「高齢者が暮らし続けられる社会の一部としての家づくり」
これまでも、
バリアフリーや手すりの設置、
段差の解消など、
高齢者向けのリフォーム・住宅提案は
一部存在してきました。
しかし、これからの時代は違います。
高齢者が“特別な存在”になるのではなく、
社会の大多数が高齢者になる時代になるのです。
つまり、すべての家が
「高齢者の暮らし」に適応している必要がある。
しかも、“建てた瞬間の高齢者”ではなく、
「いずれ高齢になる人」の未来を見越して
設計する力が問われます。
■「工務店は家を売る仕事」ではなく、「人の未来を支える仕事」
資料P19の人口ピラミッドを見ると、
若年層の割合は今後ますます減っていきます。
20年後、30年後、
40代以下の人口は今よりも1000万人以上減少し、
働き手も、子育て世代も、家を買う層も、
今より確実に細くなっていきます。
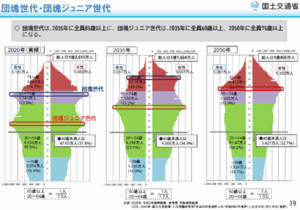
つまり、これまでの
「若い家族に新築を売る」というモデルは、
将来的には必ず縮小していく運命にあります。
そのときに工務店として
生き残るにはどうすればいいか?
「人の一生を支える住宅」
「地域に根ざした支援インフラとしての住宅」
の両方に向き合うべきだと私は考えます。
家を売るだけではなく、
「人生に寄り添う器をつくる」
ただの設計施工業者ではなく、
「暮らしの戦略パートナーになる」
これが、今後の工務店に求められる
本質的な役割です。
■ 工務店にできる3つのこと
では、実際に私たちができることは何か?
①「将来を見据えた設計提案」
若いご家族にも、
「いずれ親の介護をするかもしれない」
「自分たちが老いる」ことを見越して、
柔軟な間取り・可変性・
増改築のしやすさを最初から考える。
設計とは“未来への備え”であることを
伝えていく必要があります。
②「高齢者の住み替えを支援するリフォーム・リノベ」
高齢者が住み慣れた家を活かしながら、
安心して暮らせるようにする。
ただの段差解消ではなく、
孤立させない・支援とつながれるような
工夫を取り入れる。
近隣との動線、見守り対応、
将来的な施設対応なども意識した
住宅改修が鍵となります。
③「地域との連携と相談の窓口になる」
自治体や福祉機関、ケアマネージャーと連携し、
「住宅の相談を、最初に持ちかけられる存在」になる。
小規模工務店だからこそ、
顔が見える関係性を活かし、
地域の“住まいと支援のハブ”を担う。
■ 最後に
高齢社会の問題は、
行政や福祉の課題ではなく、
「暮らしの問題」です。
そして「暮らし」を最前線で担っていくのは、
私たち工務店の仕事です。
この人口構造の変化は、
決して“遠い将来”の話ではありません。
すでに始まっていて、
2035年は目の前です。
だからこそ、今目の前の家づくりに、
未来を見据えた視点を
一つでも多く取り入れること。
実際、当社が手掛けている家は、
耐震、断熱、気密、空気環境はもちろんの事、
”耐久性”を重要視しております。
高齢になってからリフォームする事は、
リスクが多く、理想は長持ちする住宅なのです。
私たち住宅会社は、家を通じて社会と
つながっていく事が私たちの使命だと、
私は思います。
参考資料
国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」
国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」




