
更新情報
2025年05月17日 社長ブログ 社長コラム
当たり前基準:耐震性能編
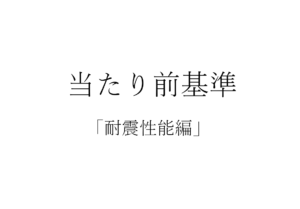
以前からブログでもコラムでも、
当社が主催する家づくり寺子屋®
まみたんセミナーなどでも何度も同じ事を
お伝えしている事があります。
せっかく家を建てるなら、
最低基準の性能を担保しましょう。
という事です。
最低基準=当たり前基準
だと考えます。
大切な事ですので、
繰り返し何度もお伝えしますが、
最低基準の性能とは、
断熱性能+気密性能
耐震性能
耐久性
上記項目となります。
あなたがどこで建てても、
金額がいくらでも新築でもリノベでも、
この項目は必須項目だと考えます。
今から建てる皆さんに
「当たり前基準」をお伝えしていきます。
今回は当たり前基準(耐震性能)編です。
2025年4月から耐震関連の法律が変わりました。
耐震の法改正については、
別記事でもYouTubeでも
同じ事の繰り返しになりますが、
当たり前基準という観点からお伝えします。
来月から何が変更になるのか?
4号特例の縮小です。
木造建築物は現在4号建築物に該当されており、
木造2階建て、平屋などになります。
木造3階建てや、中層、高層建築物に比べて、
平屋、木造2階建ては地震に壊れにくいので、
構造審査は省略となっているのが以前の4号特例です。
しかし勘違いされているのが、
新たにややこしい計算をする
必要がある訳ではなく、
今まで行ってきた構造の検討書類を
行政に提出する事になっただけの話です。
大変レベルの低い話なのです。
耐震等級は、1から3までありますが、
構造計算をしない限り、耐震等級は1になります。
4号特例の縮小とは耐震等級1の話です。
耐震性がアップする事にはならないのです。
地震が起こった際に、
最低基準の耐震等級1の家では、
あなたの資産である家が
倒壊、全壊、大規模半壊しないとは言えません。
実際に過去起こった震災では等級1の家では、
倒壊、全壊、大規模半壊などしているのです。
他方、耐震等級3を取得すれば、
あなたの家は倒壊、半壊する事は考えにくく、
資産も守られて住み続ける事が出来るのです。
このような事から耐震等級3はマストである事が、
耐震の当たり前基準と思って下さい。
因みに、耐震等級2.3は
構造計算を行わないといけません。
※耐震等級1は壁量や配置バランスの
検討のみで構造計算は不要
そして構造計算方法は2種類の方法があります。
品確法ルートか許容応力度計算ルートです。
ややこしい事を詳細に
覚えなくても結構ですので、
端的に申せば、より倒壊、全壊、
大規模半壊しない家にしたい場合は、
許容応力度計算ルートの耐震等級3として下さい。
更に、構造区画という考えを紹介します。
構造区画とは、1スパンを1Pと考えます。
※1Pの寸法はモジュールとする
1P=900mm、910mm、1000mm
というイメージです。
構造区画とは4P内のBOXを形成して、
家の間取りを作っていく事です。
4Pに囲まれたBOXとは、
3600mm×3600mmです。
※1P900mmモジュールの場合
構造区画絶対ルールとしては、
上下階にある構造区画4隅の柱直下率は100%とします。
これは難しい事ではなく、
やらないだけです。
やらないか、知らないかどっちかです。
構造区画を学ぶと、いかに間取りを
お絵描きで行っていたのかが分かるのですが、
ただ単に耐震等級3を取得すれば
良いという端的な事ではないのです。
構造区画ルールを守り、間取りを検討すると、
梁が大きくなる事もなく、柱の無駄な数も
無くなる事に繋がります。
結果、構造材が減り、
経済設計へと繋がります。
最後に制震ダンパーの話を。
耐震性能を高めるために、
耐震等級3(許容応力度計算)を行った。
そして構造区画ルールも行った。
だから安心!!
ではありません。
より安心な建物にしたいのなら、
制震ダンパーを検討して下さい。
※制震ダンパーでも沢山の種類がありますが、
詳細は別記事で書いています
何故かと申しますと、
耐震等級とは建物をガチガチに固めて、
単に建物を強くするイメージです。
例
耐震等級1ではこの壁は筋交い無しだが、
等級3なら筋交いをダブルで入れる
よって、震度1でも3でも6でも、
「耐える」考えです。
つまり、どんな地震力に対しても、
頑張ってひたすら「耐える」という事です。
しかし、震度1、2などの地震力は、
小さいからスルーしても良いかと言うと、
決してそうではありません。
小さくても地震力が
建物に影響を及ぼしているのです。
そして地震の頻度を考えて下さい。
震度1~3
震度4以上
どちらが多いですか?
これは小さい震度が圧倒的に多いのです。
その前提で考えると、
震度1~3の地震力は建物に影響を
「小さいながらもダメージを与える」のです。
実際、この問題でかなりの家が
倒壊、全壊、半壊したのが能登半島地震でした。
能登半島では1月1日の地震が来るまでに、
震度1以上の地震が数百回も発生しており、
建物にダメージをじわじわと与え続けていたのです。
そして、じわじわと建物を傷めて、
震度6強などの地震力で一気に
倒壊、全壊、半壊したと言われております。
このような事から震度1からの
地震力に対しても家にダメージを与えない、
制震ダンパーを付けていれば、
より大きな安心に繋がると考えます。
このような考えを、今後の家づくりの
当たり前基準として欲しいのですが、
あなたが依頼をする建築会社の
当たり前基準が違う場合は、
あなたの当たり前基準を伝えないといけません。
当たり前基準(耐震)の家とは、
地震の後でも住み続ける事が出来る家
地震の後でも資産が守られる家
耐震等級3(許容応力度計算)
構造区画ルールを守った家
制震ダンパーを検討する※震度1から効く制振装置
上記が当たり前基準(耐震)になります。
この情報がお役に立てれば幸いです。




