
更新情報
2025年06月22日 社長ブログ 社長コラム
情意投合の家づくり:想いが通じ合う10の対話 ~家づくりにおける「干渉と信頼」の境界線~
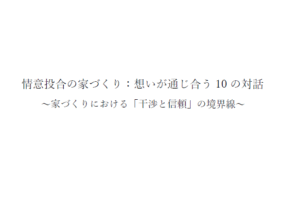
●情意投合とは
「情意投合」とは、
「お互いの気持ちが通じ合い、理解し合えること」
家づくりという人生の大きな決断において、
住宅会社と施主がこの“情意投合”を果たせるかどうかは、
完成した家の満足度を大きく左右します。
前回のコラムでは、
「家づくりは誰が主導するのか?」という視点から、
情意投合の重要性についてお話しました。
施主がリードするのか、工務店や設計士が主導するのか。
その主導のバランスによって、
家づくりの満足度は大きく変わる――
そんな気づきを共有させていただきました。
今回のテーマは、その続きです。
「どこまで任せていいのか?」
「どこまで言うべきなのか?」
つまり、
干渉と信頼のバランスの取り方について
考えてみたいと思います。
■ 全部任せるは信頼か?放棄か?
家づくりの現場で、
「全部お任せします」とおっしゃる
お客様がいらっしゃいます。
この一言、信頼の証にも聞こえます。
でも、よくよく話していくと――
・「本当はもっとこうしたかった」
・「聞かれてもピンとこなかったから流された」
・「完成してから違和感に気づいた」
という後悔の声が出てくることがあります。
つまり、「任せすぎる」ことで、
自分の理想が置き去りに
なってしまうこともあるのです。
■ 「全部決めたい」は主体性か?不安の裏返しか?
一方で、細部まで自分で決めたいお客様もいらっしゃいます。
・造作の収まりはこの写真通りにしたい
・照明の配置やスイッチの高さ
・機器の性能
その姿勢は立派だと思います。
でも、「調べ疲れて、逆に分からなくなった」
という方も少なくありません。
情報が多い時代だからこそ、
「知れば知るほど決められない」
状態に陥ることがあるのです。
■ 情意投合とは、「境界線を共有すること」
情意投合というのは、
何も「仲がいい」とか「趣味が合う」
ということではありません。
それは、
「どこまで口を出すか/任せるか」について、
共通の理解を持てている状態だと、
私は考えています。
・「この部分はプロにお任せしよう」
・「ここは自分たちのこだわりを反映したい」
・「この判断は一緒に検討してもらいたい」
その線引きを、お互いに自然な形で共有できる。
それが本当の「信頼関係」であり、
情意投合の実態なのです。
■ 「おまかせ」も、「こだわり」も、根っこは同じ
結局のところ、
・全部任せたい人も、
・全部決めたい人も、
根っこにあるのは、
「後悔したくない」という想いです。
任せて失敗するのが嫌。
でも、自分が選んで失敗するのも怖い。
だからこそ必要なのは、
プロ側からの問いかけと、導き方です。
■ プロの側にも「線引き」の責任がある
私たちのような住宅会社側にも、責任があります。
それは、単に「聞かれたことに答える」のではなく、
・「これは任せて大丈夫ですよ」
・「ここは一緒に考えましょう」
・「この判断は、◯◯を基準に考えると納得しやすいです」
といったガイドラインを示すことです。
そうやって一緒に線引きを作ることで、
お客様は安心して自分の役割を果たせます。
それが、
「干渉ではなく信頼」
「丸投げではなく委任」になるポイントです。
■ 最後に:あなたのちょうどいい距離感は?
家づくりは、ただの取引ではありません。
何十年も過ごす「暮らしの舞台」を、
共につくるプロジェクトです。
その中で、施主としてのあなたは
・どこまで自分で決めたいですか?
・どこからプロに任せたいですか?
この問いに、
自分なりの「ちょうどいい距離感」を持てているか。
それを見つけることが、
後悔のない家づくりへの第一歩だと思います。
●まとめ:
・「任せる」と「投げる」は違う
・情意投合とは、任せる/決めるの「線引き」を共有すること
・後悔しないためには、判断の責任を「共に持つ」関係性を築くこと
次回の情意投合シリーズでは、
「施主の希望とプロの提案がぶつかったとき、
どう折り合いをつけるか?」という
調和のヒントについて掘り下げていきます。




