
更新情報
2025年07月30日 社長ブログ 社長コラム
情意投合の家づくり:想いが通じ合う10の対話 ~引き渡しのあとに、本当の信頼は試される~
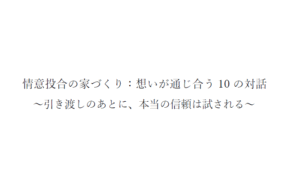
●情意投合とは
「情意投合」とは、
「お互いの気持ちが通じ合い、理解し合えること」
家づくりという人生の大きな決断において、
住宅会社と施主がこの“情意投合”を果たせるかどうかは、
完成した家の満足度を大きく左右します。
引き渡しの日。
カギをお渡しし、お客様が笑顔で家に入っていく姿を見ると、
「この家づくり、無事に終えることができたな」とホッとします。
でも本当は、ここからが始まりなのです。
家づくりにおける「本当の信頼関係」は、
引き渡しのあとにこそ試される。
今回はそんなお話をしたいと思います。
■ 家は、住み始めてから気づくことの方が多い
完成直後には分からなかったことが、
暮らしてみると見えてくる。
これは、どんな家でも当たり前に起こることです。
・スイッチの位置が少し遠かった
・光の入り方が想像と違った
・エアコンの効きにムラがある
・網戸の動きが気になる など…
住み手が実際にその家と対話しはじめて、
はじめて「気づき」が生まれます。
■ 引き渡してからの対応が関係性を決める
あるお客様から、
こんなお言葉をいただいたことがあります。
「小さなことかもしれないけど、すぐに来てくれたのが嬉しかった」
それは、ほんのちょっとした不具合――
網戸の滑りが悪かったというご相談でした。
でも私たちは、「それくらい…」とは思いません。
むしろ、そういうことこそ
一番信頼が試されると考えています。
■ 点検は「義務」ではなく、「対話の機会」
定期点検やアフター訪問も同じです。
スケジュールだから、決まりだから伺うのではなく、
「暮らしに困っていることはないですか?」という問いを届けに行くのだと思っています。
暮らしは、少しずつ変化していきます。
・子どもが大きくなった
・テレワークが増えた
・両親との同居を考え始めた
そんなときこそ、家はつくり直しではなく
育てていく対象になるのです。
■ 本当の信頼は、想定外の瞬間に試される
天災や突発的な不具合など、
「想定していなかったトラブル」に直面したとき、
住宅会社の本質が露わになります。
連絡したけど折り返しが遅い。
責任の所在があいまい。
マニュアル対応で感情が置き去り――
そんな対応をされたら、
どんなに性能が良くても信頼は崩れてしまいます。
逆に、しっかり耳を傾け、
迅速に向き合ってくれる姿勢があれば、
お客様は「この会社でよかった」と再確認してくれます。
■ 信頼とは「保証書」ではなく「姿勢」の話
保証内容やアフター制度が整っていることは安心材料のひとつです。
でもそれ以上に大事なのは、どんな姿勢でそれに向き合っているか。
・担当者が変わっても、ちゃんと履歴が引き継がれているか
・困ったときに「いつでも言ってください」と言える関係か
・問い合わせに「作業」ではなく「会話」で応えているか
これらすべてが、家の満足度ではなく、
「この人と建てた」満足感をつくります。
■ 情意投合の最終章は、「家が建ったあと」に始まる
家づくりのゴールは「完成」ではありません。
家とともに過ごす時間の中で、
ふとした瞬間に「この家でよかった」と思ってもらえること。
それが、情意投合の「最終章」であり、
私たちの仕事の「本当の意味」なのだと思います。
●まとめ
・家づくりは「引き渡し」で終わらない。そこからが本当の信頼のスタート
・暮らし始めてからの“違和感”にどう向き合うかが、信頼の分かれ道
・点検や対応は「義務」ではなく「信頼の再確認」の場
・本質は、制度ではなく“姿勢”に宿る
・情意投合とは、住まい手との関係を「育て続ける」ことでもある
●次回予告
次回は、「家づくりに正解はあるのか?」という問いをもとに、
情意投合を設計・暮らし・感性の観点から再定義していきます




