
更新情報
2025年09月30日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える:「家族構成が変われば、“ふつうの家”も変わる」
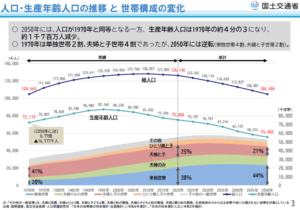
●初めに
私たちはこれまで、“家族”という言葉に、
どこか同じようなイメージを重ねてきました。
親と子ども、いわゆる「核家族」での暮らし。
戸建てに住み、夫婦と子どもが団らんを囲む。
それが“ふつうの家族”であり、
“ふつうの家”のモデルになってきました。
けれど、これからはどうでしょうか?
国土交通省の最新資料によれば、
日本の人口は今後減少を続け、
生産年齢人口(15歳〜64歳)は、
1970年に比べて3/4にまで
減ると見込まれています。
しかも、人口減よりも深刻なのが
「世帯構成の変化」です。
かつて(1970年)、
夫婦と子どもで構成される世帯は
全体の約40%でした。
一方で単独世帯(ひとり暮らし)は20%程度。
ところが2050年には、
これが逆転するとされています。
単独世帯は44%、
夫婦と子の世帯はわずか21%に。
つまり、今後の日本では“ひとりで住む”のが
“ふつう”になる時代がやってくるのです。
●“家族”のかたちは、すでに多様化している
現場に立っていても、
「家族のあり方」が
変わってきたことを、
実感する場面が増えました。
・単身赴任が長引き、平日は一人で暮らすご主人
・定年後に一人暮らしを選んだ親御さん
・結婚や出産は選ばず、一人で快適に暮らす若者
・子育てを終え、夫婦それぞれの趣味を楽しむ住まい
こうした「従来とは違う家族構成」や
「住まい方の変化」に、
住宅の設計や間取りが
追いついていないと感じることがあります。
私たちの業界は、
いまだに「4LDK+庭つき戸建て」こそが理想、
という前提で考えてしまいがちです。
でも、それはあくまで昭和〜平成時代の
“標準”にすぎません。
これからは、“一人でも心地よく暮らせる家”
“家族の変化に合わせて可変できる家”
“孤立を防ぐための地域とのつながりがある家”
こうした「次の暮らし方」を見据えた
家づくりが求められるのです。
●“個”の時代の家づくりとは
「ひとり暮らしが増える」というのは、
単に“人数が少ない”というだけの
問題ではありません。
そこには「孤独」や「見守り」「ケア」など、
社会的な課題も一緒に存在しています。
たとえば、高齢者の単独世帯が増える中で、
誰にも気づかれずに体調を崩してしまう
事例も後を絶ちません。
また、若者や子育て世代でも、
「誰にも頼れない」という孤立が深まっています。
そんな時代だからこそ、
家は単なる“箱”ではなく、
「人と人をつなぐ場所」に
なるべきだと思うのです。
家の中だけで完結せず、
近所の誰かと顔を合わせ、
声をかけあえるような設計。
将来の家族の変化に応じて、
間取りや使い方を柔軟に変えられる構造。
そういった“開かれた住まい”が、
次の時代に必要とされているのではないでしょうか。
●「家族が変わる」だから、家も変えていい
これからの日本では、
「家族」の定義がどんどん変わっていきます。
そこに“正解”はありません。
だからこそ、
「家とはこうあるべき」と押しつけるのではなく、
住む人それぞれが自分らしく
暮らせるような“器”として、
家を設計することが
私たちの役割だと考えています。
「家族構成が変われば、家も変わっていい」
これを出発点に、
これからの“家”を一緒に考えていけたらと思います。
●参考出典
国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)
該当ページ:3ページ(人口・生産年齢人口・世帯構成の推移グラフ)




