
更新情報
NEW
2025年10月04日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「“災害列島”に暮らすという覚悟。“備える家”は義務になる時代へ」
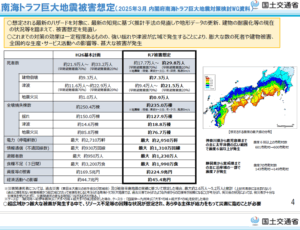
●初めに
日本に住むということは、
災害とともに生きるということでもあります。
この現実を、改めて突きつけられるのが、
「南海トラフ巨大地震」に関する国の被害想定です。
2025年3月に内閣府が発表した最新資料では、
死者数 最大29万8千人、
建物被害 235万戸以上という
衝撃的な数字が並びます。
その多くは、地震そのものではなく、
津波や火災、ライフラインの停止、
孤立による食糧不足や医療逼迫といった、
連鎖的な「暮らしの崩壊」によって
引き起こされるとされています。
■ 注目すべきは「在宅避難」というキーワード
今回の想定の中で、特に注目すべきは
「在宅避難」の重要性です。
避難所の受け入れ数には限界があり、
最大でも約950万人。
しかし、被害が想定される人口は
その数倍に達する可能性があるため、
「自宅で数日間持ちこたえることができるか?」
という視点が、
今後の家づくりにおいて
欠かせなくなります。
■ “備える家”とはどんな家か?
「耐震等級3を取っているから大丈夫」
とよく聞きます。
もちろん、構造的な強さは大前提です。
しかし、それだけでは足りません。
たとえば、
・断熱性能が低く、冬に暖房が止まれば命に関わる
・床下浸水のリスクを無視した設計では、備蓄品が使い物にならない
・高層階に暮らす高齢者は、エレベーターが止まれば避難できない
つまり、“災害に強い家”とは、
“住み続けられる家”であること。
構造だけでなく、「暮らしの持続力」が
備わっている必要があります。
■ 備えを支える「暮らしの工夫」
たとえば以下のような工夫が、
災害への備えにつながります。
・太陽光発電+蓄電池による自家発電
・備蓄品を効率的に収納できるパントリーや床下収納
・簡易トイレや給水タンクなどの設備スペース
・バリアフリー動線を意識した間取り
どれも、設計段階から意図して
組み込むことが大切です。
見た目やデザインだけでは測れない、
「暮らしの底力」が家の価値を左右します。
■ 「避難所性能」も家づくりの基準に
私たちは、家を「避難所としての性能」でも
見る時代に生きています。
・3日間、電気・水道・物流が止まっても暮らせるか?
・ご高齢の家族が安全に過ごせる構造か?
・地域の支援が届くまで、自立して持ちこたえられるか?
これらの問いに、「YES」と言える家を、
すべての住宅が目指すべきです。
■ 工務店の責任と使命
私たち工務店の責任は、
単に「丈夫に建てる」ことではありません。
家族の命と暮らしを、
災害時にも支える“器”をつくること。
そしてそれを、設計段階で丁寧に伝え、
お客様と一緒に“つくり込んでいくこと”。
「備える」という言葉は、かつては“心がけ”でした。
でもこれからは、“義務”です。
■ 「もしも」を「いつも」に変える家づくりを
災害列島に生きる私たちにとって、
「もしも」への備えを、「いつも」の
当たり前に変える家づくりこそが、
これからの“本物の価値”になると、
私は考えています。
●参考出典
国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)
該当ページ:4ページ(南海トラフ巨大地震被害想定)




