
更新情報
NEW
2025年10月15日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「長生きリスク」に住まいはどう応えるべきか? 平均寿命と健康寿命、高齢単身世帯の急増から見える課題
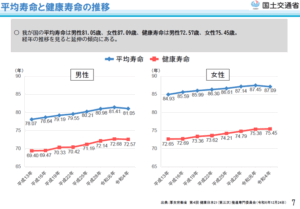
●初めに
人生100年時代。
この言葉が定着しつつある今、
住まいのあり方も変わるべき時に来ています。
国交省の資料によれば、
日本人の平均寿命は男性で81.05歳、
女性で87.09歳。いずれも過去最高を更新しています(資料P7)。
一方で、健康寿命
(介護を必要とせず自立して暮らせる年齢)は
男性72.57歳、女性75.45歳とされ、
「平均寿命-健康寿命」=要支援・要介護の期間が
男性で約8.5年、女性では約11.6年存在します。
つまり、多くの人が
「人生の最終10年前後を、
何らかの支援を必要とする状態」
で過ごすことになるわけです。
この時、もし家族と同居していなければ、
どのような住環境で過ごすのか?
これこそが、これからの
「住」の最重要課題の一つなのです。
資料P8では、
65歳以上の単身世帯数の将来推計が示されています。
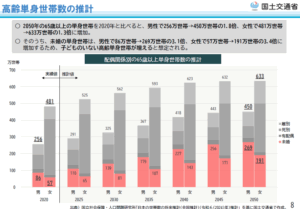
2020年時点で、
65歳以上の単身世帯は男女合わせて約737万世帯。
これが2050年には約1,083万世帯へと、
1.47倍に増加すると見込まれています。
特に注目すべきは「未婚」の高齢単身者です。
男性は86万世帯から3.1倍の269万世帯へ、
女性は57万世帯から3.4倍の191万世帯へと、
急増が予測されています。
この背景には、
未婚化や離婚率の上昇、
晩婚・晩産化など、
家族構成や人生の歩み方の変化があります。
そして結果として、
「家族と住むことを前提としない住まい」
が求められる時代へと突入しているのです。
では、私たちは何を考えなければならないのか。
家づくりのプロとして、
以下の3点が今後の重要テーマになると感じています。
●「ひとり暮らし後期」への備えとしての設計
バリアフリーや段差の解消、
手すりの設置は当然として、
「水まわりをまとめた動線」
「見守り機能のあるIoT設備」など、
自立しながらも安全を確保できる
住宅設計が必須です。
特に、2階建ての家で老後も
生活しやすい工夫が必要です。
●「孤立」ではなく「ゆるやかなつながり」へ
単身での高齢期は、
孤独や認知症のリスクとも隣り合わせです。
完全な一人暮らしではなく、
同世代との近居やコミュニティ機能を備えた
「共住型」住まいの選択肢が重要になります。
コレクティブハウスや地域コミュニティとの
連携住宅がこれからの鍵です。
●「住み替え」を前提にした人生設計
今住んでいる家が、80代・90代になったときに
本当に適しているか?
これは多くの人が見落としがちな視点です。
長寿化の中では、
1つの家で一生を完結させるのではなく、
「最適な時期に住み替える」
ライフステージ型住宅選びが現実的です。
いま私たちが取り組むべきは、
「人生の最後まで安心して暮らせる家」とは何か、
という問いに本気で向き合うことです。
高齢化・単身化が進み、
「家族がいない」
「頼れる人が近くにいない」
状態が当たり前になる時代。
だからこそ、“家”そのものに、
安心と支え合いを組み込む
発想が求められています。
●参考出典
国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)
該当ページ:7ページ(平均寿命と健康寿命の推移)
8ページ(高齢単身世帯数の推計)




