
更新情報
NEW
2025年10月23日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「住める家」と「暮らせる家」は、違う ― 住宅ストックの“本当の性能”とは?
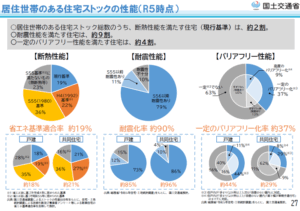
●初めに
「住宅ストックの活用」が叫ばれて久しい現代、
私たちはかつてないほど“すでにある家”をどう活かすか、
という課題に直面しています。
しかしその議論において、
見落とされがちな本質的な視点があります。
それは「今ある家が、“本当に暮らせる家”なのか?」
という問いです。
2023年時点、全国の住宅ストックのうち、
実際に居住者が住んでいる住宅に注目してみると、
驚くべき事実が浮かび上がります。
●断熱性能を満たしている住宅は、たったの2割
まず断熱性能です。
現在の基準(省エネ基準)を満たしている住宅は、
全体の約19%にとどまります。
これは裏を返せば、5軒に4軒は
“冬に寒く夏に暑い家”だということです。
特に1980年以前の基準に満たない住宅は23%、
つまりおよそ4軒に1軒は
「無断熱」に近い状態ともいえます。
仮に「住める」状態であっても、
それが「健康的で快適に暮らせる」かどうかは、
まったく別問題です。
●耐震性が不十分な家も1割
次に耐震性能。S56(1981年)以降の
新耐震基準を満たしている住宅は
79%と高い数字に見えますが、
それでも1割が耐震不足で、
1割が不明という実態です。
耐震性能の「不明」が意味するのは、
「構造上の安全性が担保されていない家」が
いまだ多数存在しているということ。
これは自然災害大国・日本において、
重大なリスクといえるでしょう。
●バリアフリー性能は“3軒に1軒”しか満たしていない
そして忘れてはならないのがバリアフリー性能です。
高齢社会が進行する中で、
段差のない玄関や廊下、
手すりの設置といった
“暮らしやすさ”の基準を満たす家は、
全体のわずか約37%。
逆に言えば、6割以上の住宅が
「老後の暮らしに向いていない家」
であるということです。
特に戸建住宅ではその傾向が顕著で、
バリアフリー化率は44%にとどまります。
マンションの方がやや進んでいますが、
それでも約29%しかバリアフリー化されていません。
- 見た目ではわからない「性能のギャップ」
外観や内装が美しくても、
「断熱性」「耐震性」「バリアフリー性」
が不足していれば、
その家は“命を守れない家”
“将来の暮らしを支えられない家”
になってしまいます。
リフォームやリノベーションが
注目されている今だからこそ、
単なる“見た目の更新”ではなく、
「中身の更新」が求められています。
●未来に残すべき家とは?
住宅ストックの性能が低いままでは、
「空き家問題」や「高齢者の住み替え難民」
といった社会課題も加速します。
今ある家を“本当に住める家”に再生させる取り組みが、
今後ますます重要になるでしょう。
逆にいえば、「性能の高い住宅を新たに建てること」もまた、
将来の社会インフラを築く行為なのです。
私たちが今つくる家が、
「50年後に取り壊される家」ではなく、
「100年後も暮らし続けられる家」であるために。
「住める家」ではなく、
「暮らせる家」を問い直す視点を、
これからの住宅づくりに持ち込みたいと思います。
●参考出典
国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)
該当ページ:27ページ(居住世帯のある住宅ストックの性能(R5時点))




