
更新情報
NEW
2025年10月31日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「“住宅弱者”という言葉に耳を澄ませてみる」
●初めに
家は、人が安心して暮らすための
「最小単位のインフラ」です。
雨風をしのぎ、
暑さ寒さから身を守り、
心が落ち着ける場所。
けれど、現実には
「住む家がない」
「家を借りられない」という人たちが、
この日本に確かに存在しています。
しかも、年々増えています。
それが、国交省の資料でも課題として挙げられている
「住宅確保要配慮者」
いわゆる“住宅弱者”と呼ばれる人たちの存在です。
今回はこの「見えにくい課題」について、
私たち住宅業界がどう向き合うべきかを考えてみます。
■「家を借りられない」高齢者たち
資料では、高齢単身者の住まいの確保が
深刻な問題として挙げられています。
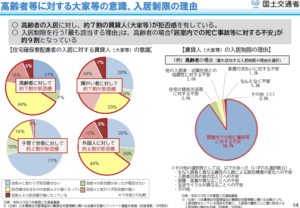
ある統計によると、
60歳を超える単身者のうち、
約3割が
「賃貸住宅の入居を断られた経験がある」
と答えています。
理由はさまざまです。
・病気や介護のリスクがあるから
・家賃を滞納するかもしれないから
・孤独死されたら困るから
これは誰かの悪意というより、
「そうなってしまう構造の問題」です。
高齢で、
身寄りがなく、
保証人もいない。
その時点で、住宅市場から
“見えない排除”が始まってしまうのです。
この問題は、
都会だけでなく地方でも深刻です。
家は空いているのに、
条件が揃わないと貸してもらえない。
保証会社の審査も年齢や
年金収入の少なさで通らないことがある。
結果として、
「高齢=リスク」という構造的な偏見が
根強く残っています。
地域の不動産業者と住宅事業者が連携し、
実態に合った支援制度や
マッチング体制を整えることが求められています。
■「住める家があっても、住ませてもらえない」
“住宅弱者”には、他にも以下のような人々が含まれます。
・シングルマザーや生活保護受給者
・外国籍の方やLGBTQの人々
・障がいや依存症などで支援が必要な方々
空き家は全国に増えているのに、
住む場所を確保できない人がいる
この矛盾の裏側には、
社会的な偏見や制度の未整備が
横たわっています。
空き家問題の裏には、
こうした“使われない資源”が眠っています。
空き家バンク制度や
市町村による斡旋も進んでいますが、
実際にはリフォームが必要だったり、
貸主がリスクを恐れて躊躇したりと、
ハードルは少なくありません。
それでも、
「空き家を誰かの居場所に変える」
という視点を持つことで、
地域に希望をつなぐ事例が
少しずつ生まれてきています。
■ 地域住宅業者として、何ができるか?
私たち工務店や住宅会社が直接
「賃貸事業者」ではなくても、
この課題に無関係では
いられないと感じています。
なぜなら、これからの時代、
住宅とは「売るだけのもの」ではなく、
「地域の中でどう活かされるか」
が問われる存在だからです。
たとえば、
自治体や居住支援団体と連携し、
空き家を「地域の福祉インフラ」として
再活用する動きも始まっています。
工務店が単なる建築業者ではなく、
“暮らしのコーディネーター”として機能すれば、
貸し手と借り手の不安を埋める
「人の橋渡し役」になることもできます。
こうした支援や調整役として、
地元の住宅事業者が
「人と住まいをつなぐ存在」になる可能性は
大いにあると思います。
■“見えない課題”に耳を澄ませる会社でありたい
“住宅弱者”という言葉を、
「自分たちには関係ない世界」と
切り離してしまうのは簡単です。
でも、いつかは誰もが年を取り、
体が思うように動かなくなり、
社会的に「弱い立場」になることは
避けられません。
つまり、“住宅弱者”は「他人事」ではなく、
「未来の自分の姿」かもしれない。
このような社会課題に対して、
“経済合理性”だけでは動けない場面もあります。
だからこそ、
小回りの利く地元工務店こそが、
柔軟に対応し、
“誰かの困りごと”に一歩踏み込める
存在になれるのではないでしょうか。
私たちは「見えにくい課題」にこそ耳を澄ませ、
“誰かの暮らし”のそばで仕事をしている責任を
大切にしたいと思うのです。
●終わりに
“いい家を建てる”だけでは、
これからの住宅業界は生き残れません。
“いい暮らしを支える会社”であるかどうか。
その問いが、
今の時代にはより重く、強く、
突きつけられています。
住まいに困っている人がいる。
家があっても住めない人がいる。
私たちのすぐそばに。
それに気づける会社、
そこに手を差し伸べられる
地域住宅業者でありたいと、
私は思います。
参考資料
国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」
国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」




