
更新情報
NEW
2025年11月04日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「“家を売らずに生きる”という選択肢」
●初めに
「老後の安心は、“家を売らずに生きる”という選択肢から」
「家を持っているのに、お金が足りない」
日本の高齢者が直面する、
そんな“静かな矛盾”が今、社会問題になりつつあります。
退職後、年金収入だけでは暮らしが成り立たない。
でも自宅は持ち家で、ローンは完済している。
いわゆる「資産はあるけど現金がない」
というケースが、今、増えているのです。
そんな背景から注目されているのが、
「リバースモーゲージ」と呼ばれる仕組みです。
■「家を担保に、お金を借りる」仕組み
リバースモーゲージとは、
持ち家を担保にして、
金融機関から老後資金を借りる制度です。
通常の住宅ローンとは逆で、
借入の返済は「その人が亡くなった後」。
つまり、「家を担保にして、死後に清算される」
ローンです。
毎月の返済が不要で、
借りたお金で生活費や介護費用に充てることができる
「家を売らずに、お金を得る」ための手段としては
理にかなっているように見えます。
国交省の資料(P11)でも、
今後の活用拡大や制度の見直しが議論されています。
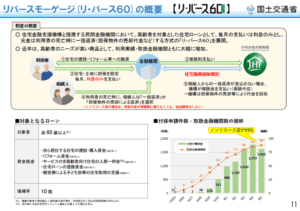
■ 増える関心、広がらない現実
しかし、現状としてリバースモーゲージは、
まだまだ一般的ではありません。
その理由はいくつかあります。
第一に、対象者や物件に制限が多いという点。
都市部の一定の評価額を満たす
持ち家でないと利用が難しく、
地方や老朽化した住宅では、
担保価値がつかないケースが多いのです。
第二に、家を子どもに残したいという感情的な抵抗。
たとえ経済的に合理的であっても、
「家を担保に入れること」に不安や
罪悪感を抱く方も少なくありません。
第三に、制度に対する不安感。
借入額が市場価値と連動するため、
将来の返済額や相続時の処理に不確実性が残ります。
「もし自分が長生きしすぎたら?」
「相続人に迷惑がかかるのでは?」
そんな不安が、制度利用のハードルを高くしているのです。
■ 「家は持っているのに不安」という現実
高齢期において、安心して暮らすには
「住まい」「健康」「お金」が三位一体で必要です。
しかし、どれだけ良い家を持っていても、
現金が尽きれば生活は立ち行かなくなります。
これは「家がある人の不安」として、
あまり語られてきませんでした。
多くの制度や支援は
「住宅がない人」にフォーカスされていますが、
これからは「住宅はあるが、活かせていない人」
への視点も必要だと、私は感じています。
リバースモーゲージは、その選択肢の一つになり得る。
ただし、それは「使えば安心」という魔法の制度ではなく、
本人・家族・専門家がしっかりと話し合い、
選び取っていくものです。
■ 私たち工務店にできること
このテーマに触れたとき、
「これは銀行や保険の話」と感じる方もいるかもしれません。
でも私は、住まいをつくる私たちこそ、
この問題に向き合うべきだと感じています。
リバースモーゲージが機能するためには、
住宅が「資産」として評価され、
長く価値を保つものでなければなりません。
つまり、その家が「安心して担保にできる」家かどうか?が、
重要になるのです。
耐震性、断熱性、維持管理のしやすさ、そして立地や流通性
そのすべてが、「老後の暮らしを支える武器」
としての家の価値に直結します。
目の前のお客様の「暮らし」をつくるだけでなく、
その人の20年後、30年後に
「この家でよかった」と思ってもらえる家を建てること。
それが、私たちがすべき「住宅支援」だと思います。
■ 最後に
リバースモーゲージは、
単なる“お金の話”ではありません。
それは、「家をどう活かして、どう生きるか」という、
人生の話です。
誰もが安心して老後を迎えられる社会にするために、
制度と家づくりの両輪で、
このテーマに向き合っていきたいと思います。
参考資料
国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」
国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」




