
更新情報
NEW
2025年11月12日 社長ブログ 社長コラム
これからの“家”を考える: 「“手間をかける人”が、いなくなる未来」
●初めに
「この収まりは、よく考えているな」
「この和室の天井、今はできる職人がほとんどいない」
家づくりの現場には、
“技術の記憶”が宿っています。
しかし今、それが静かに、
そして確実に失われようとしています。
国土交通省の資料にも記載がある通り、
建設業界では担い手不足、
特に職人の高齢化が深刻な問題となっています。
私たち地域工務店が目の前にしているのは、
単なる「人手不足」ではなく、
“文化の継承が断たれる危機”でもあるのです。
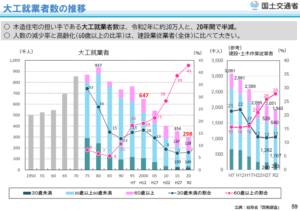
■ 技術があっても、「やる人」がいない現実
現在、住宅業界における
大工や職人の高齢化は加速しています。
・大工の平均年齢は60歳を超えている
・若手の新規参入は年々減少
・技術の継承が「現場任せ」になっている
・職人として食べていける仕組みが成り立っていない
たとえば、左官・建具・瓦・
タイル・無垢材の造作など、
「手仕事」が必要な工程は、
人が減れば一気に“選べない選択肢”になります。
つまり、技術はあるのに、
実現できないという
“未来の家づくりの貧困”が迫っているのです。
■ なぜ、若い人が入ってこないのか?
原因はさまざまですが、
主に以下のような要素が挙げられます。
・雇用の安定性が見えにくい(個人事業・弟子制度)
・給与・待遇面での不透明さ
・「泥くささ」や「キツさ」のイメージが先行
・デジタル社会との接続が弱く共感を得づらい
一方で、「自分の手で形をつくる仕事がしたい」
という若者は、
今も少なからず存在しています。
つまり、“入り口の見せ方”と“
仕組みの整備”さえ整えば、
まだ希望はあるのです。
■ 地域工務店にできることは何か?
私たち地域工務店は、
大手のように大量採用や研修制度を
整えることは難しいかもしれません。
しかし、“一人の人間を、
長く育てる現場”としての土壌は、
間違いなくあります。
地域の工務店がいま出来る事を
少し考えるだけでも沢山あると思います。
①「育てる現場」としての覚悟を持つ
人を雇い、任せ、失敗しても感情で叱らずに、
愛を持って支える。
教える時間を「無駄」とせず、
“育てることを仕事にする”
② 施工のプロセスを「見せる文化」に変える
SNSやYouTubeを活用し、
「どうやって家ができるか」を動画で発信
③現場見学会や学生向けの体験イベントを定期的に開催
職人さんの手仕事を目の前で体感してもらい、
モノつくりの楽しさを体験する。
④「食べていける仕事」にする仕組みをつくる
単価の見直し、評価制度の明確化、
技術手当など、
“技術がある人が報われる環境”を整える。
このように出来る事があるのです。
■ “工務店の未来”は、“職人の未来”でもある
今後、AIやプレカットが進み、
建築現場の自動化も
進んでいくかもしれません。
しかし、
“その家にしかできない仕事”
“住む人にしかわからない収まり”は、
最後まで人の手が必要です。
地域に根ざした工務店が、
「ただ建てる」ことだけでなく、
“職人を育てること”
そのものをブランドにする。
そんな時代が、
もう来ているのではないでしょうか。
■ おわりに
私たちの手がけた家が、
「誰が、どんな想いでつくったか」
を語れる家であってほしい。
そして、「自分もこの道を目指したい」
と思ってくれる若者が、
地域に一人でも増えてほしい。
そのためには、「技術」だけでなく、
「想い」も伝えていかなければならない。
“手間をかける人”が、
未来にも残っているように。
“育てる”ことをあきらめない
工務店でありたいと私は思います。
参考資料
国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」
国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」




